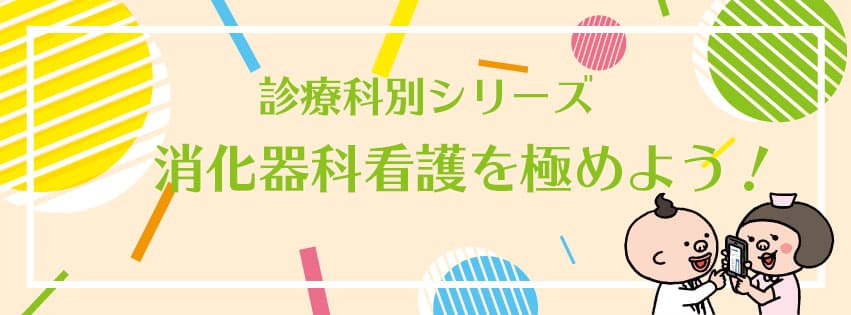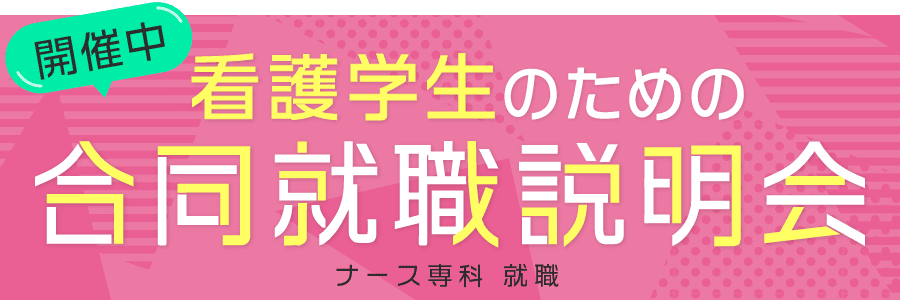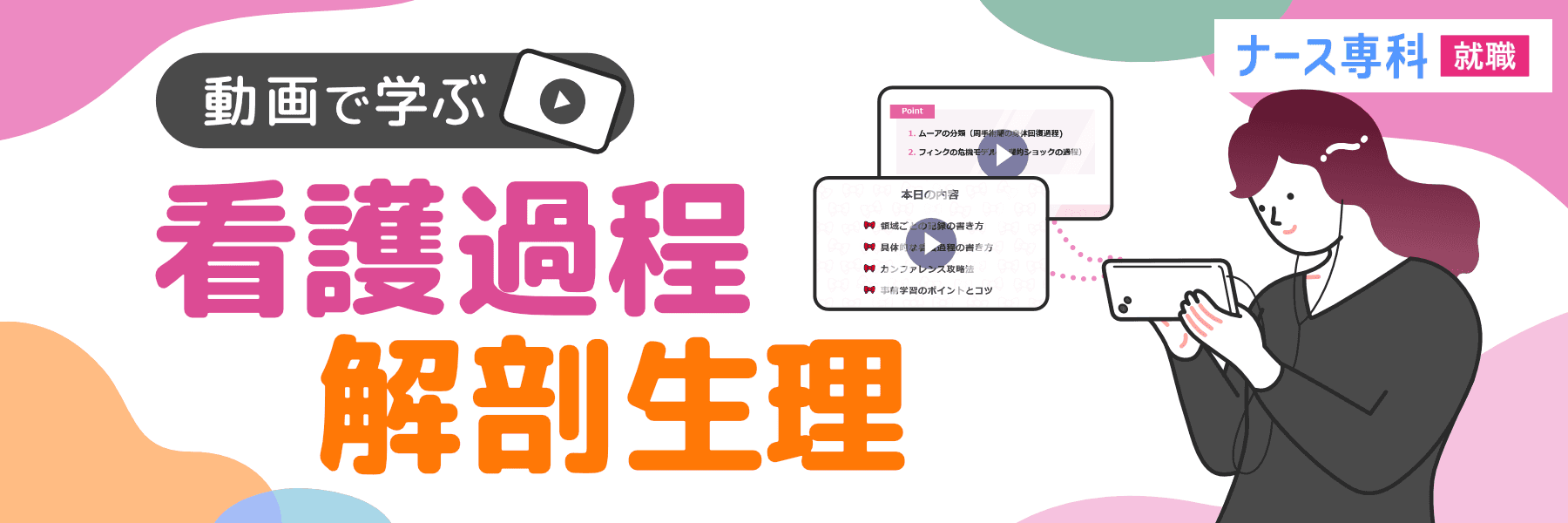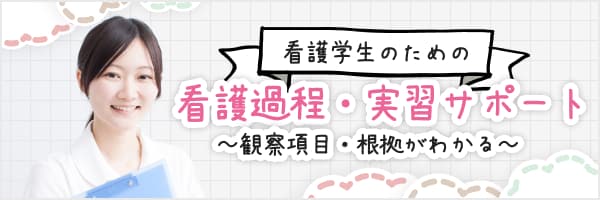- 掲示板
看護学生です。学校で安楽な呼吸への援助について演習があります。事例としては「80歳代男性。在宅酸素療法を行なっていたがタバコ30本/日吸っていた。自宅で呼吸困難が現れ受診し、COPD急性憎悪およびうっ血性心不全(NYHA3)と診断された。著明な症状として呼気性呼吸困難・喘鳴・口唇色不良がある。現在入院1日目で酸素マスク5L/分使用している...
- 掲示板
表題についてお聞きしたいです今は急性期にいますが、地域包括支援センターや回復期の勤務をしていた経験もあり、病院の生活相談員から、地域医療連携室の看護師として異動してきてほしいんだけど…と遠回しに打診されました当院の地域医療連携室には専従看護師はいません生活相談員と社会福祉士のみで運営している部署です現在は久しぶりの急性期勤務で、覚えること...
- 掲示板
訪問看護師です。膀胱がん末期でコアグラや浮遊物が多く、22Frカテーテルでも二時間ともたず閉塞してしまう方が、持続膀胱洗浄をしながら在宅へ戻られました。指示書にもサマリーにも流量は「1000~2000/日で持続膀胱洗浄をしていた」としか記載されていなかったのですが、家族からの「1日2000mlで、目安は2秒に1滴といわれた」という情報と、...
- 掲示板
輸液滴下速度について、質問させてください。大腸がんの患者様で、ターミナル期で在宅看護をされています。イレウス疑いもあり嘔吐等の症状はありませんが、腹部緊満で経口摂取もほとんどできなくなっておりビーフリード500を毎日点滴になりました。ほとんどベット上で過ごされ自力での体位変換もできないと思います。先輩ナースの指示で5時間かけて落とすように...
- 掲示板
看護師になり、12年間は急性期の病棟ではたらきました。子育て期間は、仕事をセーブするため、二年間の休職。その後は8年間パートで訪問看護の仕事をしていました。訪問看護の仕事は、自分にあっていたと思いますが、続けていくうちに、自分が臨床から離れて長くなるに連れ、自分の不甲斐なさを感じることも多くなり、いろいろなスキル面のアップをはかりたくなり...
- 掲示板
保健師資格取得について伺います。現在保健師受験資格取得のためには一年制の保健師学校か、四年制の大学に三年次またな二年次編入する、大きく分けて二つの道があるかと思います。私はこの春から高等看護専門学校の三年生に進学する者です。一般四年制大学をはるか昔に卒業して長い社会人経験を経て看護専門学校に入りました。こういうケースの場合、保健師資格を目...
- 掲示板
みなさんは接続チューブはどのように洗浄されているのでしょうか。湯や水をフラッシュするだけでしょうか、それとも酢酸を通されているのでしょうか。もしかしたら、専用ブラシをお使いになられているのかもしれませんね。ある患者さん(男)の接続チューブの汚染が強くて困っています。本来なら交換をすればいいことかもしれませんが、収入が少なく、在宅でいらっし...
- 掲示板
最近勤め始めた認知症ケア施設の併設クリニックでパートをしていましたが突然解雇されてしまいました。理由は私のやっている看護がウチの理念に合わないからということでした。私自身はケアワーカーさんのケアに何か言ったこともなく,むしろ吸引や在宅酸素療法などの高度医療ケアについて相談に乗っていたつもりでしたが,一部のワーカーさんや古くからいる看護師が...
- 掲示板
こんにちは始めて投稿します。医療現場の倫理観と道徳観を考えると、目に余るものがあります。・・・・・看護師であること自体、苦痛になることも、皆さんはこの場合どうしたらいいと思うかお聞かせください。以前の常勤の仕事場では在宅看護してましたが、ガン末期の患者様を妻からの電話連絡であり、看護師が駆けつけたところ、血の海になっていて、喀血されたのか...
- 掲示板
私は33年間病院で勤務し(54歳)、今年5月に在宅看護を中心とする会社を作りました。長年病院で看護師をしてきて病院は治療の場であって生活の場ではないと思いました。病気の時でも住み慣れた自宅で温かい家族と一緒に生活をしたい。それが本音ではないかと思ったからです。病気の人が自宅で生活をするためには家族の協力が必要です。しかし家族の人は自宅で一...